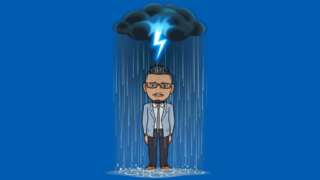学びが「誰かのため」から「自分の選択」に変わる瞬間!?
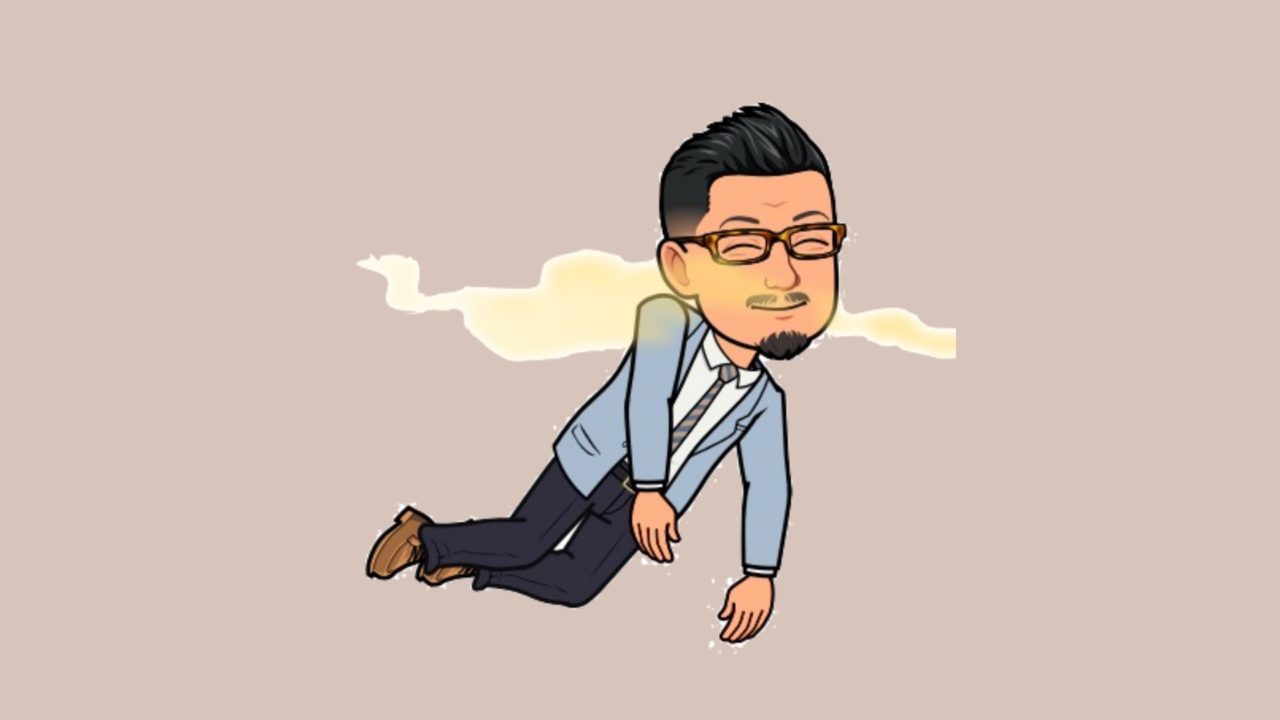
「先生、やる気が出ません。」
この言葉を、これまで何度となく
聞いてきいてきました。
テスト前、模試の後、
時には成績が上がった後でさえも、
同じ言葉が口をついて出る子はいます。
一見「やる気の問題」に見えますが、
その奥にはもっと深い「生き方の問題」
が隠れているように感じます。
今日は、そんなお話です。
「やらされる努力」は、いつか壊れる!?
誰かに褒められたくて、
怒られたくなくて、
いい子でいようとして。
子どもたちの多くは、
「期待に応える努力」
を無意識でしていることがあります。
このこと自体は、
けして悪くはありません。
しかしながら、その努力は
「他人の評価が切れた瞬間に燃料を失う」
ことがあります。
「親が言うから勉強している」
「怒られるのが嫌だから宿題をやる」
「テストの点が悪いと恥ずかしいから頑張る」
どの理由にしても、つまるところは
「他人のため」の努力ということに。
それは一時的に成果を出せても、
「長期的には必ず限界」がくるものです。
なぜなら、理由の着地点が
「自分を生きていない」からに他なりません。
「誰かを助けるように」自分を助けてみる!?
23年の講師歴の中で、
様々な生徒たちに出会ってきました。
いつも他人の顔色を伺いながら、
先生にも友だちにも「いい子」でいようとする子。
ですが、心の中ではずっと疲れている子。
じゅくちょーは覚えていなかったのですが、
そんな生徒が卒塾の際に、
こんなことを言ってくれたことがあります。
じゅくちょーは、進路相談のときに
「あなたは誰かの役に立ちたいと思ってるやね。
でもまずはさ、自分を救える自分になることから始めへん?
誰かの声なき心の声に耳を傾けられるのは、
自分の心の声をしっかりと聞ける人だと思うんよ。
自分のためにしっかりと立って歩む勇気がない人が、
人生の弱さをおぼえる状況の中にいる人を支えられへんで。」
って言ってくれたことがびっくりして。
誰かを励ますように、自分を励ます。
誰かを気づかうように、自分を気づかう。
他人を変える前に、自分を癒す。
受験も同じようなものだと思うのです。
成績を上げることは
「他人を喜ばせること」ではなく、
「自分の未来を自分の手で掴むこと」。
誰かの期待を満たすための勉強から、
自分との約束を守り自分を信じるための勉強へ。
この転換が起きた瞬間、子どもたちは変わっていきます。
「勉強=自分を知る練習」だとしたら!?
点数を上げるための勉強ではなく、
「自分が何を理解できていて、何をまだわかっていないか」
を確かめる作業として学習をする。
つまり、「自己理解の訓練」として受験勉強を位置付けると、
全く違う意味を持つのではないでしょうか。
「苦手」が見つかるのは、才能を見つけるチャンス。
「できなかった問題」は、自分の伸びしろ。
「ミスした原因」を言語化できる子ほど、後で必ず伸びる。
このように考えられるようになると、
試験は「才能の審査」ではなく、「成長の過程図」となります。
しかしながら、試験結果というものは
自分がどう捉えるかだけではなく、
周囲の人からの捉え方もあるものです。
保護者の方も、このように感じる方もおられるでしょう。
「うちの子は、やる気がある時とない時の差が激しい」
「私が言わないと動かない」
しかしこれは、子どもが
「他人軸」で動いているだけなのです。
「他人軸」で動くと、人生が苦しくなります。
誰かに決められた宿題。
押しつけられた目標。
勝手に決められた志望校。
これらは、「本人の人生への実感を奪う」ものとなり、
やがて、「どうせ頑張っても意味ない」と感じるようになります。
しかしもしそこに、
「自分で決める自由」が戻ったとしたら。
「この学校に行きたい」
「この教科を得意にしたい」
「この問題を解けるようになりたい」
という、自発的な欲求が動き出すようになるのです。
「教える塾」から「自分を取り戻す塾」へ!?
『つばさ』は、
「教えすぎない塾」です。
もちろん知識も教えますし、
解き方も指導します。
でも、それ以上に大切にしているのは
「自分で考え、自分で答えを見つける力」です。
学習とは、「自分を救う訓練」でもあるからです。
じゅくちょーは授業の中で生徒たちに、たくさん問います。
「この間違い、どんな自分が出てると思う?」
「この問題が苦手な理由、どんな思い込みがあると思う?」
解けないのは「頭が悪い」からではありません。
何度も同じミスをするのもそうです。
まだ自分を深く理解しきれていないだけ、
こう考えると、同じミスであっても
「ああ、自分にはこういう傾向があるんだな」
「ここから何をどう向き合っていく必要があるのかな」
と思考が一歩先に動き出すようになっていきます。
そこを一緒になって考えてサポートするのが、
私たち講師の役目となっている塾が『つばさ』なのです。
「自分を救える子」は、どんな壁も越えていける!?
人生では、思うようにいかないことの方が多いものです。
しかし、自分で自分を救える子は、
壁を「終わり」ではなく、「始まり」に変えられます。
- テストが悪かった → 「どこから修正しようか」
- 部活で失敗した → 「次の一歩は何だろう」
- 人間関係で悩んだ → 「私は何を我慢してた?」
このように考え方を少し変えてみることで、
自分を責めず、自分を理解していくことができるのです。
学習を通じて、その姿勢を育てることこそが教育の本質です。
勉強は、誰かに褒められるための手段ではなく、
「自分をあきらめない練習」です。
「誰かのために」頑張るのをやめてみる。
「自分のために」立ち上がる勇気を持ってみる。
あなたは、誰かに救われる存在ではなく、
自分を救える存在であり、その能力があります。
今日も、机に向かうその姿が、
未来のあなたを助けています。
自分を救える自分になろう!
なんてね(笑)
ちゃん♪ちゃん♫
いろんな質問にもここでお答えするよ!下のLINEからご質問どーぞ!
校
じゅくちょーの共著としての書籍第二弾、
『11人の敏腕塾長がこっそり教える 地方名門国公立大学 合格バイブル〜親子で読むと勉強にすぐ結果が出る!〜』
が発刊されました!
徳島という地方の受験生たちが、情報弱者として受験に対して後手に回らないためのお役立ち本間違いなし!
ぜひ、お近くの書店やAmazonにてご購入し、お手にとってお読みいただければ幸いです!(2022.8.20時点:勉強法のカテゴリーで現在17位!)
そして、第一弾となるKADOKAWAから出版された、
『自学力の育て方』も絶賛発売中です!