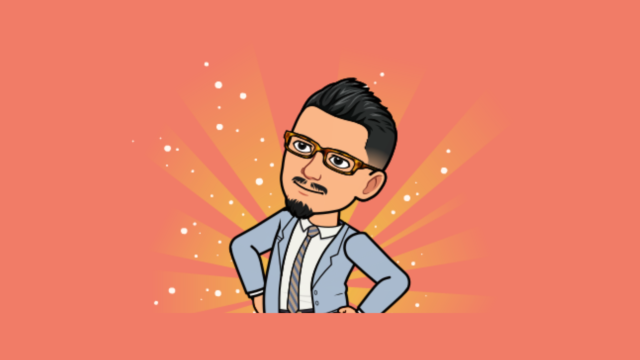理科の問題分析1回目は「生物」。
本日は「地学」に焦点を当てて解説をしてみます。
もう一度繰り返しますが、理科という教科は
もう暗記だけでできる時代は終わった!
ということを肝に銘じておいてくださいね!
どーも、塾講師歴17年、38歳3児のパパで認定心理士、上位公立高校受験・国公立大学受験専門塾、じゅくちょー阿部です。
- 本年度の入塾生は、満席となりました。
- 来年度の春期講習会からのご入塾のご予約は10名(仮)の予定です。
- 日曜セミナー『国公立大学:二次対策化学・物理・生物』は、10月4日(日)から全8回で開講します。
大問3<地学>:天気・空気の流れ
この問題で、多くの生徒が点数を落としてしまっているのではないでしょうか?
単純な語句暗記では絶対に点数が取れない内容です。
ただ、運よく選択肢が正解することはあるかもしれません。
(1)は、語句の知識問題。
①「晴れた日の夜、気温が高いのは海上と陸上のどちらか?」
海風と陸風の原理を問う問題です。
なぜどちらから風が吹くのかという原理まで理解しておかなければ解けません。
ポイントは「夜」の一言ですね。
答えは、「海上」です。
②「①のとき、上昇気流が生じているのは図1のA, Bどちらか?」
海上の方が暖かいわけですから、上昇気流も海上です。
答えは、「B」となりますね。
(2)も、語句知識問題。
海風・陸風の知識をこれでもかと掘り下げてきます。
「晴れた日の夜、海岸付近での風の吹き方は、陸から海か、海から陸か?」
海上で上昇気流が発生している訳です。
ということは、「陸から海」の風の流れとなりますね。
このように、一つの知識から枝葉を広げるような思考力の代表のような問題です。
(3)も、語句知識問題。
「(2)のように吹く風のことを何というか?」
勘違いしている生徒も多くいますが、風向の定義を知っていますか?
風向とは、ある地点に対して風がどちらの方角から吹いてくるか、を指します。
陸から吹いてくる風ですから、もちろん「陸風」が答えとなります。
(4)は、表の風向から陸と海の位置関係を推測する問題。
これはかなりの良問です。
昼間は「東寄りの風」が吹き、夜間は「西寄りの風」となっています。
昼間は海風、夜は陸風の原則から考えて、
「東側に海があり、西側に陸」が答えとなるでしょう。
いやはや、この問題の策問者はすばらしいですね!
非常にシンプルでありながら、深い思考力を求める問題です。
これからの理科学習は、こういう問題が解けるようになってもらいたいとの意図が伝わってきます。
皆さんは、いかがだったでしょうか?
大問7<地学>:地震のメカニズム
これは予想的中でした。
ですが、地震のいつものような初期微動や主要動を求める問題ではありません。
地震発生のメカニズムを問う、やはり原理の理解を求める問題でした。
やはり、深い語句理解がなければ解けない問題でしたね。
(1)は、語句の穴埋め選択問題。
図1のようにプレートには、海洋プレートと大陸プレートがある。海洋プレートは、主に太平洋や大西洋、インド洋の海底の( X )で生じる。こうして生じた海洋プレートは( X )の両側に広がっていく。海洋プレートの1つである太平洋プレートは、日本列島付近では( Y )の方向に移動している。
プレートが生じる場所を問う( X )のかっこ。
久しぶりに解答で「海嶺」と答える問題となりました。
太平洋プレートがどちらの方角に移動しているかは知っての通りですね。
答えは、「ウ:海嶺・東から西」となります。
(2)は、文章から解答を類推する問題。
Ⅰ:日本海溝から日本列島に向かって、地震の分布がだんだん深くなっている。
Ⅱ:内陸では震源の浅い地震も起こっている。
①「Ⅰのようになっている理由を「海洋プレート」「大陸プレート」の2つの語を使って説明せよ。」
これは、よく問われるいつもの問題です。
「海洋プレートが大陸プレートの下に深く沈み込んでいるから」
で大丈夫ですね。
②「Ⅱの地震は、海洋プレートの動きによって大陸プレートに力が加わり、大地にずれができることによって起こっている。このうち、過去に繰り返し活動した証拠があり、今後も活動して自信を起こす可能性のあるずれを何というか。」
はい、よく耳にする「活断層」が答えです。
ここは簡単でしたかね。
(3)は、非常に面白い思考力問題です。
太平洋プレートの中心部には、約2770万年前にできた火山島があり、太平洋プレートの動きによって、現在の位置まで約2500km移動したと考えられている。この火山島は1年間に約何㎝移動したと考えられるか。
唸りますね(笑)
正直なところ、小学4年生の算数の問題です。
ですが、できないんです。
ただ、1年間分の距離を求めているに過ぎないのですが、kmをcmに直すことができない生徒もいるのです。
250,000,000 ÷ 27,700,000 を求めるだけで大丈夫。
答えは、「ウ:約9.0cm」となりますね。
地学は、昔は「覚えるだけで大丈夫」と言われる筆頭でした。
ですが、この2問をご覧になってどのような感想をお持ちになりますか?
もう、暗記単元と言われていた生物と地学は、思考力問題の最筆頭になったのです。
第二回の基礎学の「地学」予想!?
第二回の範囲は、中3地学の「天体」が含まれないため、
中1中2の地学から第一回同様に出題されます。
中1から出題されるならば、「火山(鉱物)・地層(堆積岩)」となるでしょうか。
この範囲を重点的に復讐しておけば、点数は硬いでしょう!
中2地学は、今回同様天気からの出題です。
「飽和水蒸気量(雲の出来方)・天気図(気圧配置)」と
第二回の地学分野においては対策が立てやすくなっています。
第二回の地学分野では満点を取れるように、
演習に演習を重ねておきましょうね!
ちゃん♪ちゃん♫
2020年度『つばさ』の授業日程は、ここからご確認できます。


.png)